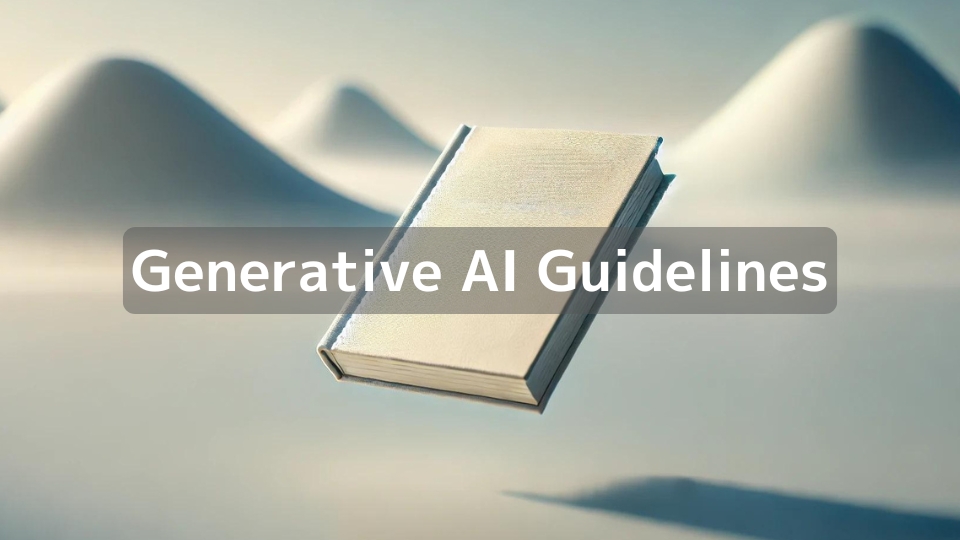こんにちは!ムララボです。
生成AIの利用が急速に広がる中、さまざまな組織や政府機関がガイドラインを策定しています。これらのガイドラインは、生成AIを安全かつ効果的に活用するための指針を提供しています。以下に、主要な生成AIガイドラインをまとめましたので、参考にしてください。
「ガイドライン」であるとしていますが、それぞれの立ち位置における、その時点での生成AIなどのAI技術の活用に関する考え方や指針となっています。
1. 経済産業省・総務省のガイドライン
経済産業省と総務省が提供するガイドラインでは、生成AIを含むAI技術を安全に、安心して使うための基本ルールが記載されています。AIを使う際のリスクや、どうやって安全に使うかなどが書かれていて、ビジネスでAIを活用する人には特に役立つ内容です。
「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を取りまとめました
令和 6 年 4 月 19 日 総務省 経済産業省
2. 文化庁のガイドライン
次に、文化庁のガイドラインでは、生成AIを使って作った作品が他人の著作権を侵さないようにするためのルールが説明されています。AIでイラストや文章を作るときに、他人の作品を無断で使っていないか確認するのに役立つ内容です。
AIと著作権に関する考え方について
令和6年3月 15 日 文化庁
AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス
令和6年7月31日 文化庁
3. 内閣府のガイドライン
内閣府のガイドラインでは、AI技術が広まる中で、知的財産権(発明や創作物などの権利)をどう守るべきかがまとめられています。AIがますます進化する中で、どうやって自分の権利を守りながらAIを活用するかを考えるのに役立ちます。
AI時代の知的財産権に関する検討会 中間とりまとめ
2024 年5月 AI 時代の知的財産権検討会
4. 文部科学省: 初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン
文部科学省が提供するこのガイドラインは、初等中等教育の現場で生成AIをどう利用するかについての指針を示しています。教師が生成AIを活用して教材を作成したり、個別指導に使ったりする際のポイントや、リスク管理の方法が具体的に説明されています。
初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン
令和5年7⽉4⽇ ⽂部科学省
5. デジタル庁のガイドライン
デジタル庁のガイドラインは、生成AIを使うときにどんなリスクがあるのか、そしてそれをどう防ぐかにフォーカスしています。AIを使っているときに、予想外のトラブルを避けるためのポイントが紹介されています。
• テキスト生成AI利活用におけるリスクへの対策ガイドブック(α版)
2024年6月10日更新 デジタル庁
(8月初旬に確認)
6. 経済産業省の「コンテンツ制作のための生成AIガイドライン」
経済産業省が提供する「コンテンツ制作のための生成AIガイドライン」では、生成AIを使ったコンテンツ制作のプロセスが詳しく説明されています。コンテンツを企画する際のポイントや、生成AIサービスを選ぶ基準、法的なチェックポイントなどがまとめられており、特にクリエイティブ業界にとって役立つ内容です。
コンテンツ制作のための生成AIガイドライン
2024.7 経済産業省
7. 日本ディープラーニング協会(JDLA)のガイドライン
最後に、JDLAのガイドラインは、生成AIを含むディープラーニング技術を安全かつ効果的に使うための内容がまとめられています。AIを使う際に、ユーザーデータの取り扱いや著作権の注意点、またリテラシー向上のための教育が詳しく書かれています。
• JDLA(一般社団法人日本ディープラーニング協会)のガイドライン[資料室]
2024年2月(更新) 一般社団法人 日本ディープラーニング協会
ガイドラインをどう使うか?
これらのガイドラインは、それぞれ違う視点から生成AIの使い方や注意点を教えてくれます。たとえば、AIを使って作品を作るなら文化庁のルールを参考に、ビジネスで導入するなら経済産業省のガイドラインが役立ちます。教育現場での利用を考えている場合は、文部科学省のガイドラインが特に参考になるでしょう。
ホームページ運営において、生成AIを活用する際には、コンテンツの合法性と品質が非常に重要です。経済産業省の「コンテンツ制作のための生成AIガイドライン」は、著作権やデータの適法性に関する注意点を網羅しており、特に商業利用の場面で避けるべきリスクを詳細に説明しています。このガイドラインを参考にすることで、法的に安全で質の高いコンテンツを作成し、安心してホームページ運営ができるようになります。生成AIの力を最大限に活用しながら、信頼できるコンテンツを提供していきましょう。